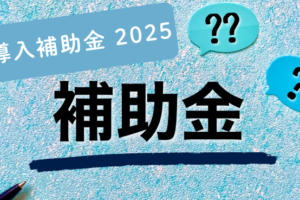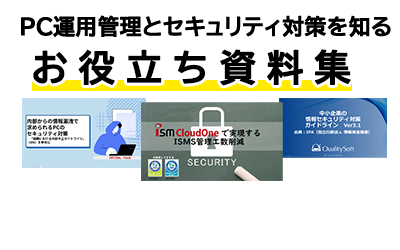企業におけるIT環境は、PCやスマートフォン、サーバー、ソフトウェアなど多種多様な資産で構成されています。これらを適切に管理できていないと、セキュリティリスクの増大やライセンス違反、余計なコストの発生といった問題が生じかねません。そこで注目されているのが 「IT資産管理」 です。
本記事では、IT資産管理の基本的な考え方から、導入の目的・メリット、さらに効率的に運用するためのおすすめツールまで、IT資産管理が初めての方でも理解できるよう解説します。これからIT資産管理の導入を検討している情報システム部門の担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
1:IT資産管理とは?
IT資産管理とは、企業が保有する ハードウェア(PC、スマートフォン、サーバーなど)やソフトウェア、ライセンス、クラウドサービスの利用状況を一元的に把握・管理する仕組み のことを指します。
解決できる課題
従来は表計算ソフト等を用いた手作業による管理が主流でしたが、企業のIT環境が複雑化した現在では、手作業ですべての資産を正確に把握するのは困難です。特にリモートワークの普及により、従業員が自宅や外出先などの社外ネットワークからシステムにアクセスするケースが増えています。その結果、管理対象となる端末や接続環境が多様化し、IT資産の管理は従来以上に複雑で難しくなっています。さらにモバイル端末や私用デバイスの利用拡大、SaaSサービスの普及によって、ライセンスの管理が一層複雑になっています。
IT資産管理を適切に行うことで、以下のような効果が期待できます。
- 利用していないPCやライセンスの無駄を削減
- セキュリティリスクや不正利用を未然に防止
- IT監査や法規制にスムーズに対応
- 情シス担当者の作業負担を軽減
つまりIT資産管理は、単なる「資産の棚卸し」ツールではなく、企業全体のIT活用を最適化し、リスクを軽減するための基盤といえます。
2:IT資産管理が必要な理由
なぜ多くの企業がIT資産管理に取り組む必要があるのでしょうか。背景には、セキュリティやコスト、コンプライアンスといった重要な課題があります。ここでは、IT資産管理を導入する主な理由を解説します。
セキュリティリスクの増大
近年、サイバー攻撃や情報漏えい事件が相次いでいます。会社や組織で管理されていない端末やソフトウェアが存在すると、脆弱性がそのまま放置される可能性が高くなり、その結果として不正アクセスやマルウェア感染の温床となりかねません。特にOSやアプリケーションのアップデート漏れは、悪意のある攻撃者に狙われやすいポイントです。IT資産管理を行うことで、利用状況を把握し、セキュリティリスクを最小限に抑えることが可能になります。
ライセンス違反の防止
SaaSなどクラウドサービスの普及により、ライセンスの契約・利用状況を正しく把握・管理することが難しくなっています。ライセンス数を超えた利用や、契約期限が切れたソフトウェアを利用し続けることは、法的なトラブルや高額なペナルティにつながる恐れがあります。IT資産管理を通じて、ライセンスの利用状況を正確に把握することは、コンプライアンス遵守の観点からも不可欠です。
コストの最適化
利用していないPCやスマートフォン、不要なソフトウェア、使用されていないアカウント、重複契約しているクラウドサービスなどは、企業にとって無駄なコストとなります。企業に存在する資産の全体像を可視化することで、不要な契約を見直したり、未使用の資産を有効活用したりすることができます。結果として、ITコストを大幅に削減することができます。
3:IT資産管理の主な目的
IT資産管理を行う際に重要なのは、「何のために管理を行うのか」を明確にすることです。単にIT資産の一覧を作るだけでは意味がなく、企業のリスク低減やコスト削減、業務効率化といった目的を達成してこそ効果を発揮します。ここでは、企業がIT資産管理を導入する主な目的を整理して解説します。
IT資産の「見える化」
まず最も基本となるのは、すべてのIT資産を正確に把握することです。PCやモバイル端末(タブレットやスマートフォン)、サーバー機器、ソフトウェアのライセンス、SaaSやクラウドの利用状況などを一覧にして、現状を「見える化」することで、不要な資産や利用状況の偏りを発見できます。
たとえば、部署ごとにどのようなソフトウェアを利用しているのかを把握できていなければ、契約の重複や未使用のライセンスを放置したままにしてしまうリスクがあります。また、他部署に貸し出したパソコンや、外部委託先に貸与した端末がどこにあるかを把握できなければ、端末の紛失による情報漏えいのリスクが高まります。「見える化」を徹底することこそが、余計なコストや情報漏洩のリスクを防ぐ最も基本的な手段であり、IT資産管理のスタートラインとなります。
適正なライセンス管理
ライセンスの過不足は、単なるコストの問題にとどまらず、コンプライアンス違反や法的リスクにつながる可能性があります。利用可能な数を超えてソフトウェアを使えば契約違反となり、高額な違約金や訴訟リスクを招く恐れがあります。一方で、実際には使用していないのに契約を更新し続けているケースもあり、無駄なコストを生み出してしまいます。
IT資産管理を始めると、誰がどのライセンスを利用しているのかを正しく把握でき、必要な人に必要な分だけ最適に配分できます。これにより、コストの適正化とコンプライアンス遵守を両立できるのです。さらに、ライセンスの更新期限や利用状況を自動的に確認できる仕組みを導入すれば、担当者の負担も大幅に軽減されます。
セキュリティの強化
端末のOSやソフトウェアを更新せずに放置していると、セキュリティリスクは確実に高まります。また、社内ネットワークに管理していないPCが接続されることも大きなリスクです。OSやソフトウェアの脆弱性を突かれれば、攻撃者にとって侵入の入口となり、組織全体のセキュリティを脅かす可能性があります。また、誰がどの端末を利用しているかを把握できていなければ、悪意を持った退職者や委託先等の関係者が、不正にシステムにアクセスするリスクも否定できません。IT資産を常に把握しておくことは、こうしたリスクを未然に防ぐ「脆弱性の管理」や「不正利用の防止」の第一歩です。セキュリティを強化するためには、資産を見える状態にし、常に最新の状態に保つことが欠かせません。
おすすめ
IT監査対応の効率化
監査や規制対応では、IT資産やライセンスの使用状況を証跡として提示する必要があります。IT資産管理を人手に依存しない持続的な管理体制をつくっておくことで、監査への対応がスムーズになり、業務の負担を軽減できます。
4:IT資産管理ツール導入のメリット
IT資産管理ツールを導入することで、企業は単にIT資産を整理できるだけでなく、業務効率化やコスト削減、セキュリティ強化、さらには内部統制の強化といった多くのメリットを得られます。ここでは、情シス担当者が特に注目すべき代表的なメリットを解説します。
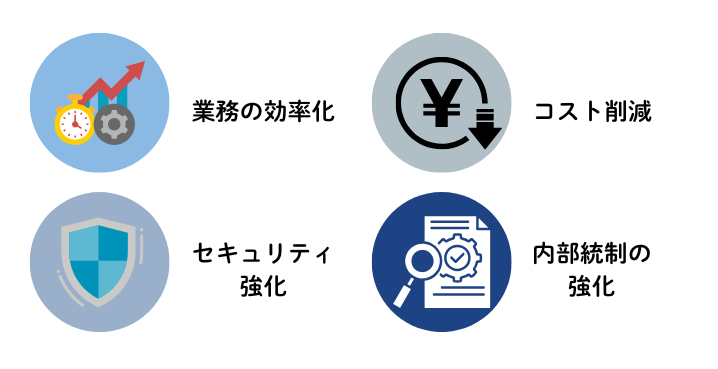
業務の効率化
表計算ソフトを使った従来の管理方法では、台帳の更新や棚卸し作業に膨大な時間と労力がかかっていました。専用ツールを用いることで、端末やソフトウェアの情報を自動的に収集・更新できるようになるため、棚卸しや台帳管理などの手作業が大幅に削減されます。その結果、情シス担当者は定型業務に時間を取られず、DX推進に関する業務など、より戦略的なIT改善や業務サポートに時間を使えるようになります。
コスト削減
使用されていない端末や重複契約のライセンスを特定できるようになるため、無駄な契約を削減できます。活用されていないIT資産やライセンスの有効活用も可能となり、IT予算をより効率的に配分できます。
セキュリティ強化
IT資産の可視化により、脆弱性のある端末や更新が止まったままのソフトウェアを迅速に特定できます。適切なタイミングでのOSのアップデートや、脆弱性のある端末の利用を停止することで、情報漏洩や不正利用のリスクを低減できます。
内部統制の強化
監査や社内規程・法律の適合確認のために必要な情報を即座に提示できるようになり、担当者の負担を減らせます。また、情報を一元管理することで、社内規程や法規制への対応力も向上します。
5:IT資産管理の手法とステップ
IT資産管理を実際に始める際には、「何を」「どの順番で」管理していくかが重要です。正しい手法と段階的なステップを踏むことで、効率的に管理体制を整え、導入効果を最大化できます。ここでは、代表的な手法と導入のステップを解説します。
IT資産管理の主な手法
1. 棚卸し(インベントリの管理)
現在、企業で保有している端末(PC、スマートフォン、サーバーなどのハードウェア)とソフトウェアライセンスやクラウドサービス等を一覧にします。ここでは、手作業ではなく、管理ツールを使った自動収集を組み合わせることで精度が向上します。
2. ライフサイクル管理
購入から廃棄までの資産のライフサイクルを管理します。IT資産の取得日、利用者、利用状況、保守・更新期限などを追跡することで、資産の最適化とコスト削減につながります。
3. ライセンス管理
ソフトウェアやクラウドサービスの契約状況を把握し、ライセンスが必要なところに適正に配分します。契約の期限や利用状況を可視化することで、過剰な契約や有効期限切れの利用を回避できます。
4. セキュリティ管理
組織の管理下にある端末やソフトウェアの状態(どの端末に何が入っているのか)を把握し、更新や脆弱性対策を実施します。また、端末の利用権限を設定したり、アクセス履歴を追跡(ログを取得)することで、不正利用のリスクも低減できます。
導入ステップの例
1. 目的の明確化
「3:IT資産管理の主な目的」で述べたように、まず社内で管理の目的を明確にして対象とする範囲を定めます。
2. 管理ルールの策定
IT資産の登録方法、ライセンス更新の手順、利用状況の確認方法などを決め、社内ルールとして整備します。
3. 現状把握
企業内で管理すべきIT資産をリスト化し、台帳やツールに登録して、現状を把握します。
4. ツールの選定と導入
自社で管理する対象や課題を明確にしたうえで、課題を解決するための機能を比較検討し、IT資産管理ツールを導入することで、運用効率を高めます。
5. 導入計画の策定と検証
いきなり全社に展開するのではなく、まずは特定の部署で試験的に導入し、運用を開始します。ここでは、動作確認や運用手順、トラブル時の対応方法等を検証し、改善点を洗い出すことが重要です。
6. 全社展開
本格的な全社展開にあたっては、まず運用ルールを策定し、全従業員が共通の基準でシステムを活用できる体制を整えます。次に、操作方法やトラブル対応を理解してもらうため、従業員教育やマニュアルを整備します。その際に、問い合わせ窓口も併せて案内しておくと、運用をよりスムーズに進められます。
7. 運用・改善
導入後は定期的な棚卸しや利用状況の確認を行い、ルールや管理方法を継続的に改善していきます。これにより、IT資産管理の精度が高まり、運用効率やセキュリティ強化にも繋がります。
6:IT資産管理ツールの選び方
IT資産管理を手作業で行う場合、管理対象が少ないうちは対応できるかもしれません。しかし、台数が増えるにつれて工数は膨大になり、更新漏れや情報の不整合といったリスクが高まります。効率的かつ正確に管理を行うためには、専用ツールの導入が欠かせません。ここでは、IT資産管理ツールを選定する際のポイントをご紹介します。
ツール選定のポイント
IT資産管理ツールを選ぶ際には、いくつかのポイントを確認しておくと導入後の運用がスムーズになります。
オンプレミス製品かクラウド製品か
まず確認したいのは、オンプレミス製品かクラウド製品かという点です。オンプレミス型は、自社のサーバーにシステムを構築して利用する方法で、セキュリティポリシーを自社の基準で厳格に運用できる点が特徴です。一方で、サーバーの維持管理やサーバーのバージョンアップにコストや手間がかかり、導入後もシステム担当者の負担が大きくなりがちです。
一方、クラウド型はインターネット経由でサービスを利用できるため、初期費用を抑えてスピーディーに導入できるのが魅力です。特にテレワークや複数拠点で働く従業員の端末も一元的に管理できるため、昨今の働き方に適しています。また、サーバー管理やセキュリティ対策はサービス提供側が行うため、自社の運用負担を軽減できる点もメリットです。導入環境や運用体制に合わせて、自社に適した形態を選ぶことが重要です。
管理したい端末のOSが対象となっているか
管理対象となるOSをしっかり確認しておくことが重要です。多くの企業ではWindows端末が主流ですが、近年ではクリエイティブ部門や企画部門などでMacが導入されるケースも増えています。また、営業担当者が利用するスマートフォンやタブレットなどのモバイル端末も、業務上欠かせないIT資産となっています。もし導入するツールがWindows専用であった場合、Macやモバイル端末の利用状況を把握できず、資産管理に抜け漏れが生じる恐れがあります。特に、モバイル端末は持ち出しの機会が多く、セキュリティリスクが高いため、管理対象としてカバーできるかどうかは重要なポイントです。社内で利用している端末の種類を洗い出し、それぞれのOSに対応したツールを選ぶことで、管理の一元化とセキュリティの強化を実現できます。
必要な機能が搭載されているか
端末やソフトウェアの情報を自動で収集できる自動収集機能があるかどうかは重要です。また、ライセンス更新や脆弱性、未使用端末などを自動で通知してくれるアラート機能も、管理の漏れを防ぐために欠かせません。さらに、リモートワーク環境や分散拠点でも活用できるクラウド対応かどうか、そして管理状況やコスト、セキュリティリスクを分かりやすく可視化できるレポート機能があるかも確認しておくと安心です。
他にも、機能が多すぎるツールは管理の複雑化につながることもあります。IT担当者が必要とする機能が揃っているか、操作性や使い勝手が良いかどうかも、ツール選定の重要なポイントになります。
おすすめのIT資産管理ツール
ISM CloudOneは、端末(PC、サーバー、モバイル端末)の情報を自動で収集し、一元管理が可能です。クラウド製品のため、初期のシステム構築負担が少なく、スムーズに導入できます。オンプレミスの環境では管理が難しい、テレワーク中の端末も簡単に管理できます。
また、ライセンス管理やパッチ管理、操作ログ管理など豊富な機能を備えており、脆弱性を通知するアラート機能も完備しています。さらに、管理状況やセキュリティリスクを可視化できるレポート機能があり、業務効率化とセキュリティ強化を同時に実現できます。
おすすめ
7:まとめ
IT資産管理は、企業のIT環境を効率的かつ安全に運用するために欠かせない取り組みです。PCやモバイル端末、サーバー、ソフトウェア、SaaSサービスなどの資産を正確に把握することで、無駄なコストの削減やセキュリティ強化、内部統制の向上など、多くのメリットを得ることができます。IT資産管理を導入する際は、IT資産の現状把握や管理ルールの策定、ツールの活用といったステップを順序立てて進めることが重要です。特に、自動収集や通知機能、レポート機能が充実したツールを活用することで、効率的に運用しながらリスクを最小化できます。
これからIT資産管理の導入を検討している情シス担当者は、まず自社のIT資産状況を可視化することから始めましょう。目的と効果を明確にしながら運用体制を整えていくことが成功のポイントです。適切なIT資産管理を実施することで、企業全体のIT運用をより安全・効率的に改善することが可能になります。